創刊70年を越える『朝雲』は自衛隊の活動、安全保障問題全般を伝える
安保・防衛問題の専門紙です
前事不忘 後事之師
第118回 米国の対日石油禁輸を再考する 官僚組織の中で指導者の統制を貫徹することは容易ではない
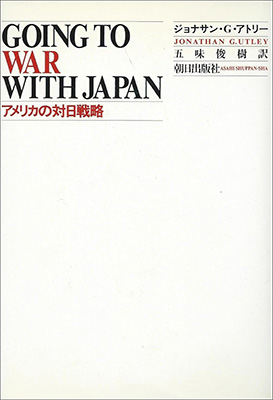
前回の連載では、1941年の米国の対日石油禁輸措置がどうして日本の真珠湾攻撃につながったのかについて青山学院大学の土山實男教授の著書を基に説明しましたが、土山がその著書で引用している米国の歴史家ジョナサン・アトリーの『GOING TO WAR WITH JAPAN』という本には、驚くべき記述があります。それは、ルーズベルト大統領は日本に対して、石油の禁輸を発動したが、輸出制限であり全面禁輸などするつもりはなかったというものです。
ルーズベルトはヒトラーのドイツと日本という二方面からの脅威を受けて、欧州第一主義の観点から、先ずはドイツ打倒に全力を振り向けるべきとの考えでした。従って対日政策は原則的には強硬姿勢をとりながらも、戦争を回避し種々の牽(けん)制(せい)策によって日本の軍事的膨張を抑止するというものでした。
1941年6月の独ソ戦の勃発を受けて7月2日に行われた日本の御前会議の「南部仏印に進駐するとともに、独ソ戦の戦況が日本にとって有利に進展すれば北進(対ソ戦)を行う」との決定をマジック情報(暗号解読情報)によって事前に知ったルーズベルトは、8月1日に日本資産の凍結と石油の禁輸措置を採ることを決めましたが、対日強硬策は日本の攻撃を誘発する恐れがあるとの海軍などからの意見を踏まえ、石油の禁輸はあくまで輸出制限とし、全面禁輸をしないように指示していました。
しかしながら措置の実施に関わっていた対日強硬派の国務省のアチソン次官補は大統領の意向に反して、石油購入に必要な凍結資金の解除を行わず、全面禁輸となりました。ルーズベルトは9月上旬になって石油の対日輸出が全面的にストップしていることを知りましたが、その状態を“容認”します。
なぜ容認したかについて、アトリーは「石油の供給を1カ月も止めてそれを再開することは、アメリカは日本に屈服すると断言している日本の強硬派の立場を強めることとなると考えた」と説明します。
しかし川田稔名古屋大学教授はその著書「武藤章」で異なる説明をしています。ルーズベルトが日本への石油輸出が全面的に止まっていることを知った同じ時期にルーズベルトのもとにチャーチル経由でソ連のスターリンから書簡が届き、そこにはヒトラーの突然の侵攻によって始まった独ソ戦においてソ連は死滅寸前の敗北の危機にある旨が記されていました。
もしソ連がドイツに屈服すれば、再びドイツがイギリス本土侵攻に向かうことになり、その時にはイギリスに本格的な危機が訪れます。仮にイギリスが敗北すれば、アメリカの安全保障にとっても許容できない状況となります。一方、日本は独ソ戦開始の事態を受けて、独ソ戦の成り行き次第で北進(対ソ戦)するという決定をしており、北進の準備も兼ねて関東軍を増強して、ソ満国境で「関東軍特種演習」を実施します。
対独戦で苦境に陥っていたソ連軍が東部で日本軍の攻撃を受ければ、ソ連にとって最悪の事態になると強い警戒感を抱いたルーズベルトは日本の対ソ攻撃の阻止を企図し、それが9月の石油の全面禁輸の容認につながったと川田は説明します。石油の供給を止めれば、日本は石油を求めてさらに南方の蘭印に向かわざるを得なくなり、日本の北進は難しくなるとの判断でしたが、同時に日本の南進はやがて英米と戦争状態となることから、川田は「ルーズベルトは対日戦争を賭してもソ連崩壊を食い止めようとしたのである」と書いています。
日本の陸海軍首脳部・幕僚のほとんどは米国の領土でもない南部仏印に進駐したからといって米国が強硬な石油の全面禁輸を行うことを予想していませんでしたが、アメリカの石油禁輸措置を受けて北進は延期され、陸海軍は対米英開戦を決意する方向に向かいます。こうした川田の説に従えば、「独ソ戦が日本の運命を変えた」ことになりそうです。
私には、ルーズベルトが石油の全面禁輸を容認した理由はどちらが正しいのか判断できません。しかしながら、後に大統領が容認したとは言え、大統領の意図に反してアチソン次官補が採った措置が重大な日本の開戦決定につながったことは明白です。
我が国では、戦前の軍隊は時の政府の統制を無視して独断専行し、それが戦争につながった大きな要因だと主張されていますが、より民主的な制度を有していた米国においても大統領の意向に反する措置が下僚によって採られ、それが重大な結果をもたらしたことは驚くべきことです。
民主主義国家であろうがなかろうが、内部にさまざまな見解の対立を抱え、かつ固有の利害を有する巨大官僚組織に政府指導者の統制を貫徹させるのは容易ではないと思います。
鎌田 昭良(元防衛省大臣官房長、元装備施設本部長、防衛基盤整備協会理事長)
