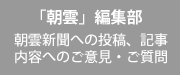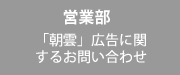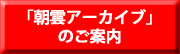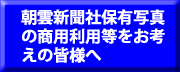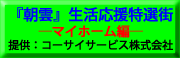第53回 テロリズムを考える
私たちを打ち負かせるのは私たちだけ

『朝雲』は自衛隊の活動、安全保障問題全般を伝える安保・防衛問題の専門紙です。
前事不忘 後事之師
 |
|---|
ユヴァル・ノア・ハラリ著『21Lessons』(河出書房新社刊)
私と同世代の方であれば、2001年9月11日の同時多発テロで、ニューヨークの世界貿易センタービルが崩壊する衝撃的な映像は今も眼に焼き付いていると思います。昨年、日本語訳が出版されたイスラエルの歴史家ユヴァル・ノア・ハラリ氏の手になる『21Lessons―21世紀の人類のための21の思考』を読んでいたら、その中にテロリズムについて鋭い分析があるのを見つけました。
ハラリ氏は、テロリストを食器店に巣くう〝微力なハエ〟に譬(たと)えます。
「ハエは微力なので、ティーカップ一つさえ動かせないが、牛を見つけて耳の中に飛び込み、ブンブン羽音を立て始める。牛は恐れと怒りで半狂乱になり、食器店を台無しにする。これこそ9・11テロの後に起こったことだ。イスラム原理主義者たちはアメリカという牛を激怒させ、中東の食器店を破壊してもらった。今や彼らはその残骸の中で隆盛を極めている。そして世界には短気な牛がいくらでもいる」
テロリストが微力かどうかは、議論があります。しかし、ハラリ氏は9・11テロ後に世界でテロで亡くなった犠牲者数が、交通事故や大気汚染あるいは糖尿病で亡くなった人数に比較して圧倒的に少ない事実を挙げて、テロリストは「微力だ」と主張します。また、将来の核テロ、サイバーテロ、バイオテロの脅威は深刻ですが、それでも、他の大きな脅威とのバランスある対応をとるべきと言います。
ハラリ氏は、テロの戦略は人々に「恐れ」を広めることで政治情勢が変わるのを期待するものだとし、こんな指摘をしています。
「テロリストはわずかな人を殺害することで無数の人に命の危険を感じさせる。そのような恐れを静めるために政府はテロの惨劇に対し、安全の誇示で応じ、特定地域の全住民を迫害したり、外国に侵攻したりして、大きな効果を狙って力を大々的に見せつける。ほとんどの場合、テロに対するこの過剰な反応の結果は、私たちの安全にとって、テロリスト自身よりも大きな脅威となる」
「私たちは、テロリストが何をしようと私たちを打ち負かせないことに気がつかねばならない。私たちを打ち負かせるのは私たちだけであり、それはテロリストの挑発にのって過剰反応した場合に限られる」
この「私たちを打ち負かせるのは私たちだけだ」という指摘は〝戦略の格言〟に入れてもよいくらいの言葉だと私は思います。個人でも不運な出来事があると、パニックになり、自滅することがありますが、国家も大惨事に際して、冷静な叡智(えいち)に基づき行動できるかどうか、自身との戦いが必要です。
他方で、自身との戦いと言っても、個人と国家との間には大きな違いがあります。
9・11テロの3日後、米国のブッシュ大統領は、未だ巨大な煙が上がっている世界貿易センタービルの崩壊現場を視察します。残骸に覆われた現場で作業にあたる救助隊員、消防隊員たちは、大統領を囲みながら、激高し「USA!」と連呼しながら「絶対に復讐しろ」と叫んで、正義の裁きを要求しました。復讐しろと要求するのは、国民の冷静な叡智ではなく、感情の発露ですが、国民の感情に応えるのも政治家の使命であり、国民に見える形で対応しなければ政権の正統性が問われることになります。
しかしながら重要なことは、対応が過剰であってはならないということです。ハラリ氏は、面白い比喩を使って過剰反応を戒めます。
「テロリストは、敵対する国家に不可能な課題を突き付ける。それは、いつでもどこでも国民全員を暴力から守れることを立証することだ。テロリストは、ひどい手札を配られたギャンブラーのようなもの。そのようなギャンブラーはカードをシャフルし直させようとする。相手国が不可能な任務を果たそうとした時、政治というトランプのカードをシャフルし直させ、思いがけずエースを配ってくれることをテロリストは期待している」
クラウゼヴィッツの『戦争論』にある〝三位一体論〟を援用すれば、国民の「激情」を政府の「理性」がコントロールできなくなれば、テロリストにエースを配ってしまうことになります。困難なことですが、政府には、テロリストの思う壺に陥らないように行動する、という冷静で賢い舵取りが要求されます。
鎌田 昭良(元防衛省大臣官房長、元装備施設本部長、防衛基盤整備協会理事長)
朝雲新聞社の本
当ホームページに掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。すべての内容は著作権法によって保護されています。