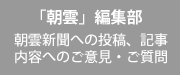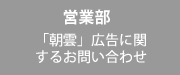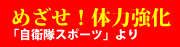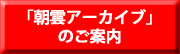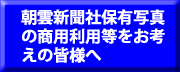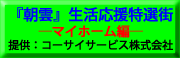第1回 生き恥をさらした男―司馬遷

『朝雲』は自衛隊の活動、安全保障問題全般を伝える安保・防衛問題の専門紙です。
前事不忘 後事之師
作家の武田泰淳は、司馬遷を「生き恥をさらした男」と書いています。司馬遷とは、『史記』を書いた中国の歴史家です。この司馬遷が、なぜ生き恥をさらしたと評されているのでしょうか?
時は、前漢の武帝時代(在位・前141年~前87年)、西方の遊牧民である匈奴(きょうど)が中国への侵略を繰り返していました。このため、武帝は、匈奴征伐のため、李陵(りりょう)という将軍を派遣。当初、李陵は匈奴に対し奮闘しますが、結局、匈奴の捕虜になってしまいます。武帝に仕えるほとんどの役人が捕虜になった李陵を批判するなか、司馬遷は、正義感から武帝の前で李陵を弁護しました。しかしながら、皇帝の前で事実と異なることを述べたとされ、司馬遷は死罪に処せられることに決しました。
当時、死罪を免れるためには二つの方法がありました。一つは五十万銭という金銭を払う方法ですが、彼には蓄えはなく、また金銭的助けをしてくれる友人、親戚もいませんでした。もう一つ、死罪から免れる方法がありましたが、それは、男子の機能を切り落とす「宮刑」という残酷な刑罰を受ける方法でした。
この時、本当は司馬遷は死にたかったのだろうと私は思います。しかしながら、彼には死ぬに死ねない事情がありました。それは、司馬遷と同じ「大史令(たいしれい)」という職にあった父から、父が書き著そうとして果たせなかった漢までの歴史を完成してくれと遺言されていたからです。司馬遷は父の遺言を聞きながら、「誓って、父上の整理された旧聞をひとつあまさず論述いたします」と泣きながら答えたと伝えられています。
司馬遷は父との約束を守るため、男子として最も忌むべき刑罰を受け、生きながらえながら『史記』を書きあげます。
驚くことに、この時の自身の気持ちを司馬遷が書き残した文書が現在に残っています。友人の任安(じんあん)に宛てた手紙「報任少卿書」がそれです。この手紙の中で、司馬遷は自ら、「詬(はじ)は宮刑より大なるはなし」として、「この恥辱を思うにつれ、腸が一日に九回捻じれるような苦痛におそわれる」と書いています。
私のような鈍感な人間でも、この時の司馬遷の気持ちを推測すると、目頭が熱くなってきます。しかしながら、司馬遷は恥辱のどん底の中で、苦悶しながらも、孔子、屈原(くつげん)、孫臏(そんぴん)、韓非(かんぴ)といった後世に偉大な業績を残した人物の生涯を思い浮かべ、彼らが全て逆境の中で、鬱積した感情を込めて、名著と呼ばれる書物を書きあげたことを思い出しました。そして「自分も上古より現在にいたる歴史をまとめあげることによって、一家の言を成そう」と決意しました。
こうして、百三十篇、五十二万六千五百字からなる『史記』が生まれ、中国の「二十四史」の最初のものとして、世界史上、最高の歴史書の一つとして位置づけられています。
今から10年ぐらい前の私の現役時代のことですが、防衛省のある先輩から、「最近の若い奴は理屈ばかりで、仕事に対する思いが足りない」と言われたことがありました。『史記』という書物が憤りをバネに書かれた背景を知るにつけ、仕事、特に後世に残るような仕事をする上には、怒りや憤りをバネにした岩をも貫く強い「思い」が不可欠だと感じます。
鎌田 昭良(かまた・あきら)
昭和55年4月防衛庁入庁。平成9年イギリス国防大学留学。官房広報課長、秘書課長、審議官兼情報本部副本部長、沖縄防衛局長、報道官、官房長、装備施設本部長などを歴任し、平成26年7月退職。東大経済学部卒。千葉県出身。60歳。現在、東京海上日動顧問、ベナン共和国大使館大使特別顧問。
朝雲新聞社の本
当ホームページに掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。すべての内容は著作権法によって保護されています。