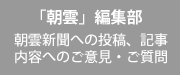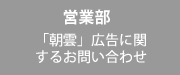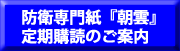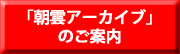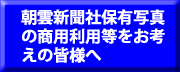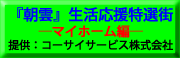第44回 太平洋戦争の開戦の決定から学ぶもの
――堀田江理著『1941決意なき開戦』を読んで

『朝雲』は自衛隊の活動、安全保障問題全般を伝える安保・防衛問題の専門紙です。
前事不忘 後事之師
 |
堀田江理著『1941決意なき開戦』
3年ほど前、本屋の新刊コーナーに置かれていた『1941決意なき開戦』という本をたまたま目にし、著者が堀田江理という女性であることに興味を覚え読んでみました。
この本は1941年の太平洋戦争開戦直前に、当時の日本の政治・軍事の指導者たちが「御前会議」や「大本営政府連絡会議」において、どのように議論を重ねて開戦に向けて意思決定を行ったのか、そのプロセスを明らかにしたものです。
私は、この本が指摘しているとても重要な事実は、当時の我が国の意思決定がヒットラー独裁下のドイツなどと異なり、圧倒的な決定権を持つ独裁者によって行われたものではなく、文民政治家と軍部の指導者がいくつもの「連絡会議」、「御前会議」を経て行った共同作業であったことだと思います。
著者は「1941年の4月から12月にかけて日本の指導者たちが行った一連の決定の多くは、開戦に向けて運命の経路を形作っているという認識のされぬままに、なし崩し的に合意がなされ、ひとつひとつと決断を重ねていくうちに、日本政府の身動きできる余地が確実に失われ、(ほぼ勝ち目のないと認識されていた戦争に向かっていった)」と書いています。
エリートであるはずの各組織のトップたちが繰り返し議論を重ねたにもかかわらず、なぜ「最悪の選択」をすることになったのか、その理由は会議体形式の意思決定に潜む〝落とし穴〟にあることをこの本は示唆しているように見えます。
第一の落とし穴は、会議の出席者が自らが代表する組織の利益のみを主張し、国家全体にとって何が重大であるか、覚悟を持って主張することがなかったことです。1940年7月から開戦直前の1941年10月まで首相を務めた近衛文麿は、天皇家に次ぐ高貴な家柄の出で国民の人気も高かったのですが、公の会議の場で強く開戦を主張する軍部に対峙し、自分の意見を押し通すことができませんでした。米国との開戦になれば正面に立つことになる海軍に「米国との戦争に勝機はない」と主張してもらうことを頼みにしていました。
他方で、海軍は戦いに勝機がないことを認識しながら、公の会議の場でそう言わされることから逃げていました。また、陸軍参謀本部や海軍軍令部のトップは好戦的な部下の幕僚たちに後押しされ、部下に「弱腰」であると見られないよう、芝居がかった強気の発言をしていました。
昭和天皇は米国との戦争に大きな懸念を示されておられましたが、明治以来の天皇の統治の在り方に反するとして、自らが拒否権を発動することはなされませんでした。
会議体形式の意思決定に潜むもう一つの落とし穴は、意見の対立が生じた際にしてはいけない「妥協」が安易に行われたことです。
近衛文麿首相は暗転する日米関係を打開するため、ルーズベルト大統領との首脳会談を目指します。会談を軍部に受け入れさせるため、戦争準備の必要性を唱える軍部と妥協し、外交交渉に期限を設定し、期限までに外交が実を結ばない場合は開戦を辞さないことを決定します。首脳会談が実現できれば米国との戦いは避けられるので、開戦時期の設定は意味がなくなると考えたようですが、交渉が行き詰まってくると、期限が既成事実化し、戦争準備が独り歩きしていきました。
堀田氏はこうした落とし穴を要約するかのように、本の中で「指導者たちは、意見の相違を徹底的に話し合うよりは合意に達することを好んだ」と書いています。
太平洋戦争の開戦から80年近くの歳月が経過しました。しかしながら、あの戦争を「総括」することは、未だ容易な作業ではないと思います。ハル・ノートに代表される米国の頑な対応に開戦の原因があったとの指摘もありますが、この本の著者は勝ち目のない戦争に向かったその原因は、主に「日本の外よりも内側にあった」と主張します。
戦後、我が国は戦争への反省から民主主義国家に国の体制を改めました。そこでは大きな問題が生じた時には、関係者で議論を積み重ねることが大事であり、そうすれば必ず良い結論が得られ、失敗はしないとの考えが支配的です。しかしながら、80年近く前の歴史は残念ながらそれが正しいとは限らないことを教えているようです。
鎌田 昭良(防衛省OB、防衛基盤整備協会理事長)
朝雲新聞社の本
当ホームページに掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。すべての内容は著作権法によって保護されています。